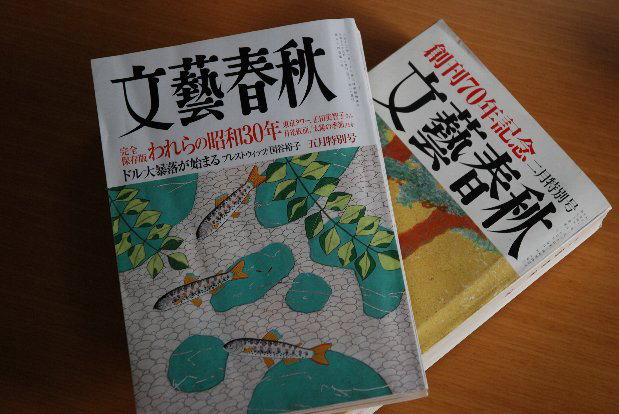051. 赤蕪は暖かい旅の味 赤 蕪 / 福島県舘岩村

福島県南会津地方、舘岩村産の赤蕪である。収穫したばかりの蕪を、庭先を流れる小川に浸し、年寄りたちが腰をかがめてごしごしと泥を落としていた。周りの山が賑やかな紅葉から褐色へと変化し、弱まる日差しに空気が冷たく感じるようになった晩秋の一日、通りがかりに撮った一枚である。ごらんのように舘岩産の赤蕪は、形はさまざまで中には丸型のものもあるが、たいていは不恰好に小さな大根状をしているのが特徴のようである。
一般に赤蕪は古くから地方の山地、つまりは高地の焼畑で栽培されてきたとのことである。毎年お盆のころに種を蒔いて晩秋のいまごろが収穫時期になるという。この地方でないと赤く育たないのだとも聞かされて、村のお店で土産代わりにしたのが「赤蕪漬け」であった。うすいピンクの落ち着いた色合、噛めばシャキシャキとした歯ごたえ、そしてほどよい上品な味が良い。
山形県温海地方の赤蕪もよく知られているが、それは確か丸型のいわゆる「かぶ」のイメージにぴったりの姿をし、色も強い赤色で、歯ごたえがもっとしっかりして、野性味を感じる大人っぽいやつだったように記憶している。温海系か舘岩系か、どちらを選ぶかは好みの違いが決めることであろう。
ここ南会津地方、とくに舘岩村周辺はあまり交通が便利な土地とはいえないが、それだけに山々が集落を暖かくとりかこんだ景色は、四季それぞれに見事である。思わず絵筆でも執りたくなるような衝動にかられる。近年になって、温泉が人を呼んでいるとも言う。深い山を背にした湯の花温泉があり、そこから木々の生い茂った峠を越えると、秘湯として知られる木賊温泉がある。湯船が深い谷底の流れのすぐ渕にある温泉である。聞けば台風などの大水のときは川が氾濫し、土砂が押し寄せて、そのたびに掻き出して復元しなければならないという。もっとも私には秘湯趣味などないので、いかにも秘湯とは大変なところにあるものだと感心したことだった。
さて、近ごろはメールを使えば欲しいものはなんでも産地から直接手に入るので、私たちは、季節になると思い出したようにこの赤蕪を少しばかり注文し、味わいながら訪ねたころをなつかしんでいるのである。 (2007/11/29)